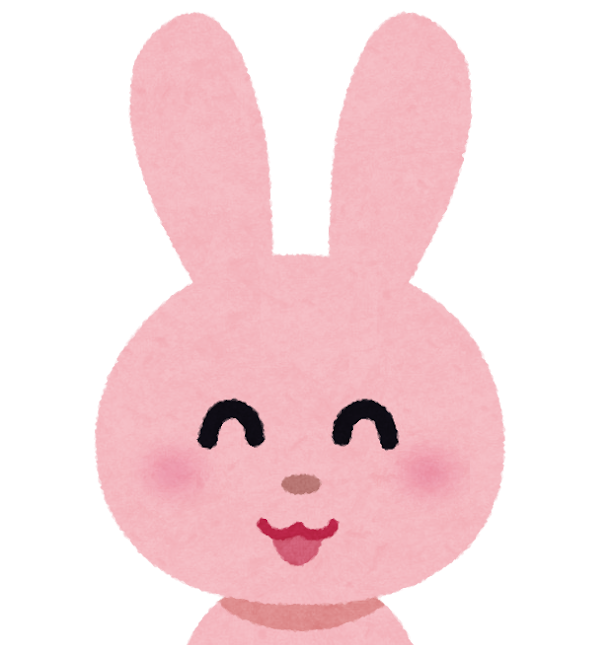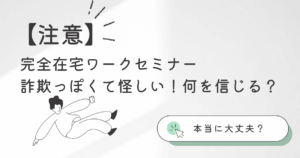何度か在宅ワークについて調べていたということもあり、インスタやヤフーを開くと在宅ワークに関する広告をよく目にするようになりました。
おしゃれでキラキラしている広告が多く、興味を持ってクリックすると、良いことばかりかいてあります(広告なのでそれもそうなのですが…)。
では、実際に以下のサイトについて調べてみました。
よく見かける広告にはどんな企業がある?
①Famm

Fammスクールは、
子どものことを第一に考えながら働きたい!
しっかりとスキルを身につけて経済的に自立したい!
子どもの手が離れるタイミングを見据えて仕事に復帰したい!
というママからの声を受けて2019年3月に開講したスクールです。
未経験からWEBデザイナーを目指すというスクールですが、WEBデザイナーの他にも動画クリエイターやグラフィックデザイン、WEBマーケティング講座などもあります。
子育て中のママのためにできたスクールなので、子どもがいても安心なシッター制度があり、仕事と育児の両立を応援してくれるスクールです。仕事と育児の大変さを私はまだ経験していませんが、なるべく子どもと関わりたいという気持ちが大きいママには適したスクールなのかなと思います。
②SHElikes

SHElikesは、
45種類のスキルから選び、好きなことを見つけて学ぶことができる!
入門コースもあり、未経験でもしっかりサポート!
月1回のコーチングでキャリアプランや強みを明確化!
SHEが紹介する企業の仕事案件で実績が作れる!
という女性向けのオンラインスクールです。
スクールを挫折させないサポート体制には月1回のコーチング、一緒に学んでいる仲間のコミュニティ相談、特別イベントなどもあります。
公式HPは若い女性が好みそうなかわいらしい雰囲気なので、HPを読むのも楽しいです。また、受講生の体験談は20代女性が多く起用されており、若い女性がターゲットな感じがします。テレビCMもよく見るので、自然と目に入ることが多いスクールです。
各スクールの料金について
①Famm
- 基本料金:184,800円(税込)
- 分割払い:最大24回まで可能
- 対面受講:基本料金に加えて追加料金が発生
- MacBookレンタル:基本料金に加えて追加料金が発生
- リスキリング支援制度:条件を満たせば最大50%オフ
②SHElikes
・基本料金:レギュラープラン 受講料162,000円 (税込) +入会金88,800円(税込)
スタンダードプラン 受講料16,280円 (税込)/月 +入会金162,800円(税込)
・分割払い:最大24回まで可能
・対面受講:月に1回コーチングあり(追加料金なし)
・転職支援制度:転職に成功し、1年以上の勤務で受講料の+20%を追加キャッシュバック
やはり、スクールを受講するとなるとそれなりの費用がかかりますね…
数万円なら出せる!と思っていましたが、十万円以上になると簡単に出そうと思えないのは私だけでしょうか。
確かに、スクールに通って学ぶという知識に対してお金を払うということをケチってはいけないのですが、余剰資金がない私にはなかなか難しい。
在宅ワークを勧めるスクールの体験談
在宅ワークを勧めるスクールを調べるとかなりたくさんあります。上記の2社は特に大きな企業なので危なそうとか詐欺っぽいという感じはしないのですが、実際に上記のスクールに通っていた方々の体験談を見ていきましょう。
- 経験豊富な講師による直接指導で、効率的に学べる
- 仲間と学べる環境がモチベーション維持につながる
- 実務で役立つスキルが身につく
- 卒業後も応用講座を受け続けられる
- 無料のシッター派遣がある
- 自分に合った働き方を見つけられる
- 様々なスキルや知識を幅広く学習できる
- 費用が高い
- 講師の質にばらつきがある
- デザインよりもコーディング中心のため、デザイン力を深めるには物足りない
- 卒業後の就職サポートが十分でない
- 独学と併用しないと、スキルが不十分
- 自分でスケジュールを組んで学習するのが大変
- 実践機会の不足、実務レベルまでは相当な努力が必要
費用面での負担が大きいことは、受講生も同じです。しかし、高額だと思うほど、頑張って仕事にしようという意気込みも大きくなるのかもしれません。
もし私がえいや!!っとスクールを受講し始めたとしたら、元をとらないとという考えで必死で頑張りますもん。そう思うと、やはり高額だと思いつつも自分が頑張る活力として費用面は将来への投資として考えた方が良いのでしょうか。
スクールに通って良かったという口コミを見ていると、過去の自分がまずは一歩踏み出したことを褒めてあげたいという口コミが目に入りました。確かに、迷っている段階では何も始まっていない状況と同じだよな…と自分自身にも同じことが言えると思いました。
かといって、スクールを受講します!!!と即決はできませんが…
費用面やサポート内容、その後どのように仕事として成り立っていくのか、そして在宅ワークとしてやっていけるのかということを柱にして、今後も在宅ワークの情報を探っていきます。